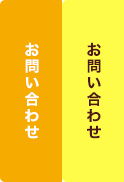愛媛慈恵会について
ABOUT EHIME JIKEIKAI
施設・事業紹介
愛媛慈恵会について
ABOUT EHIME JIKEIKAI
施設・事業紹介
- トップ >
- 愛媛慈恵会について >
- 施設・事業紹介
施設概要

東 寮

西 寮

地域交流ホーム「栄松館」

第1小規模グループケア施設

第2小規模グループケア施設

ながのホーム
- 事業所名
- 社会福祉法人 愛媛慈恵会
- 実施事業
- 児童養護施設
- 所在地
- 松山市束本二丁目13-3 【 MAP 】
- 電話番号
-
089-921-1035
- FAX番号
-
089-921-1045
- 理事長
- 栗田 欣志郎
- 創立年月日
- 明治34年7月26日
- 施設長
- 徳丸 和行
- 入所定員
- 80名
- 職員構成
-
- 施設長
- 1名
- 事務長
- 1名
- 指導員・保育士
- 25名
- 心理療法士
- 1名
- 看護師
- 1名
- 栄養士
- 1名
- 調理員
- 4名
- 家庭支援専門相談員
- 2名
- 里親支援専門相談員
- 1名
- 自立支援専門相談員
- 1名
- 建物
-
- 東寮(鉄筋コンクリート3階建・1,499.62㎡)
- 西寮(鉄筋コンクリート3階建・488.55㎡)
- 第1小規模グループケア施設(木造スレート藁平屋建・105.99㎡)
- 第2小規模グループケア施設(木造スレート藁2階建・165.61㎡)
- 地域交流ホーム「栄松館」(鉄筋コンクリート2階建・377.78㎡)
事務所・炊事


家庭料理を基本にしたメニュー
「安心・安全な施設作り」を目指しています
ここ事務所では子どもたちの成長を見守り、安心して過ごせるよう心を込めてサポートを行います。また、「働きがいのある、働きやすい職場」を目指し、処遇改善を図ることも日々の業務としております。
人事・総務・経理を担う愛媛慈恵会の中枢部所として、児童養護にふさわしい明るく広々とした空間、そして温かな雰囲気の中でスタッフも笑顔で業務に取り組んでいます。
炊事・食堂では健康的な食生活をサポートしています。特別な食事制限やアレルギーのある子どもへの配慮もしっかり行われており、安心して食事を楽しむことができます。育ち盛りの子どもたちの食が満たされ、笑顔で「ごちそうさま」と言ってくれる声にスタッフも元気をもらい、明日の調理への意気込みが増します。嫌いなものが少しでも減らせるよう工夫を凝らし、子どもたちの成長に寄り添っています。

次長兼事務長 小掠 なぎさ
男子班

「子どもたちに寄り添いながら」
様々な悩みや不安を抱えた子どもたちに、安心して過ごせる環境を整え、子どもらしく成長していけるよう、職員は協力しスキルを磨き、子どもたちに寄り添い、子どもたちの声に耳を傾け、個々を尊重した支援を行っていきたいと思います。
子どもたちが目標も持てるよう、そして、その目標に対して努力をし、達成できるよう支えていきます。また、子どもたちにとって身近な大人として人間関係、協調性を学べるお手本となるようチームワークを大切にしていきます。
我々職員に最も大切なことは、子どもたちとの“信頼関係”であると考えます。子どもたちに安心を与えられる職員となれるよう、日々、試行錯誤しながら、信頼関係を築くために努力している毎日です。厳しいことも伝えなければならない時もありますが、子どもたちのために何が大切かを最優先に考え、しっかりと向き合い、子どもたちの未来に繋げられる支援をしていきたいと思っております。

男子1班リーダー 田坂 竜馬
女子班

子どもを受け止め“育ち”を支える
西寮(女子班)は明るく笑顔あふれる空間の中で、子どもたちを受けとめ“育ち”を支える場所です。そのためのプライベートな空間として、一人ひとりが安心して過ごせる個室を設けています。自分にとっての安全地帯があることで、それぞれのペースで周りと関わることができるようになっています。
充実した余暇を過ごせるようにも配慮し、定期的にイベントや外出を企画し、季節の行事や、スポーツイベント、音楽鑑賞など、様々な分野を体験できる楽しい時間を確保しています。普段の生活も大事にして、みんながよく過ごせるためのルールを学ばせ、相手を思いやる心を育みます。そんな中で、私たち職員が安心して心を委ねられる存在となれるよう努めています。
子どもたちの声を聴き、思いに寄り添う態度を理想とし、その子にとって何が最善の利益であるかを考え追求しています。皆が情緒あふれる心優しい子へと育ってくれるよう職員皆で支援していきたいと思います。

女子班リーダー 高須賀 詩織
女子班一時保護班
家庭的な、健やかであたたかい生活を
女子班一時保護班は、今年度新しく発足しました。女子班内に設置されますが、未就学児の男女を対象とし、女児だけでなく、皆が仲良く生活できる環境づくりを目指します。とはいえ、着替えの際はスペースを分けたり、男女で入浴しない等配慮すべき点には心を配っていきたいと考えています。
当会に一時的に滞在するため、まずは不安に思ったり、寂しさを感じたりすると思いますが、職員があたたかい態度で寄り添い、リラックスできる環境を提供します。お預かり中にお子さんの発育のお手伝いをし、三育(知育・体育・徳育)の観点から養育に努めます。厳しさよりも、家庭的なあたたかさを第一に据え、身辺自立を目指します。家庭に戻ったときに一つでも「成長している!」と喜んでいただけたら幸いです。
生まれたての班ですので、試行錯誤しながらの取り組みにはなりますが、職員のチームワークは抜群。協力しながら、安心・安全で健康な生活を送れるよう、尽力いたします。

女子班一時保護班リーダー 宇都宮 なつき
第1小規模

家庭のような暖かさを感じられる場所
第1小規模は、今年度は小学生2名、中学生3名で生活がスタートしました。平屋のため、皆がリビングに集まることが多く、コミュニケーションが取りやすいのが第1小規模の魅力です。また、対面式キッチンであるため、職員から子どもたちの様子が見えやすく、会話が弾みます。調理をしている職員の姿も見えやすいため、すすんでお手伝いをしてくれます。
家庭のような暖かい日常で育まれる思いやりの心は、社会性を構築していく過程でとても重要になります。それに加えて、家族単位でのお出かけなど、安定した人間関係の中で積み重ねる経験が、自立した生活を営む力に繋がります。
第1小規模が子どもたちの安心できる場所となるよう、私たち職員はいつも間近で見守りたいと思います。そして、良いお手本となれるよう、切磋琢磨し合いながら共に成長していきたいと思います。

第1小規模リーダー 矢野 智美
第2小規模

自立に向けた、温かな暮らし
第2小規模は、現在女子中高生6名が生活しています。リビングにはいつもみんなが集まり明るく賑やかな毎日を過ごしています。各自に1人部屋があり、プライベートな時間も大切にできる環境です。趣味や学習など、1人ひとりが自分のペースで生活できるよう配慮しています。また将来自立した社会生活が送れるよう、生活習慣の確立や学力向上を基盤に、子どもたちと一緒に料理を作るなど家庭に近い環境で実践的な経験や学びを支援しています。
一般常識やマナーをはじめ、自己管理や人間関係など大人になるための大切な経験を少しずつ積み重ねていく時期でもあります。中学生は高校受験、高校生は進学・就職・一人暮らしなど、それぞれの未来に向けて進んでいきます。そんな中でも自分らしく、一歩ずつ自立に向けて成長できるよう寄り添い支えています。
子どもたちがどんな時も安心して暮らせるよう、これからも職員みんなで温かく見守りサポートしていきます。

第2小規模リーダー 岡﨑 麻理子
ながのホーム

自立のための生活力を身に付ける
ながのホームは、地域の皆様に温かく迎えて頂いてから、開設3年目を迎えることができました。 今年度は、小学生と中学生、高校生の3名での生活をスタートしました。引き続き、開設時のホームコンセプトである“施設から家庭へ”を念頭に、家庭的な生活が送れるよう運営して参ります。
ホームでは、日課やルールなどは必要最低限として、日ごろから常識を持って行動し、周囲から信用を得られる人になることを目標に声掛けを行っています。
生活の中では、特に食事に重点を置き、栄養面・食育を考慮しながら、「お腹空いた~」と帰ってくる子どもたちのために、お腹一杯食べてもらえるよう職員も腕を磨いております。また将来のため、お遣いや調理、洗濯やゴミ捨てなど当たり前の経験を積むことや、地域の皆様や友人との交流も積極的に行い、良好な人間関係を築いてほしいと考えております。
子どもたちにとって、自分の家だと思えるホームを目指して頑張っていきたいと思います。

ながのホーム ホーム長 長野 翔
心理カウンセリング

安心とコミュニケーションを通じて
カウンセリング(心理療法)は公認心理師の資格を持つ心理療法担当職員が担当しています。子どもの心理的な問題の解決や心の健康回復を目的として、週に1回50分のカウンセリングを実施しています。
特にプレイセラピー(遊戯療法)では『安心とコミュニケーション』が重要です。ストレスや不安が高まっている子どもにとっては、誰にも邪魔されずに安心して遊べる時間と場所が何よりも大切だからです。そして遊びの中のコミュニケーションを介して、心の悩みや問題について子どもが自ら自然と話せるように促していきます。物を投げたりしない等の最低限のルールはありますが、遊ぶことも話すことも子どもの自主性が尊重されていて、強制されるものではありません。
遊びの種類は様々で、パズルやカードゲーム、ボードゲームの他にビーズ等を使った創作も含まれます。また室内でだけでなく、子どもが希望する場合は屋外でのびのびと体を動かして遊ぶこともできます。

臨床心理士 永江 史朗
-

栄松館
-

トレーニングルーム
-

面会室
その他の事業紹介
自立支援
卒寮後も安心して相談できる場所の構築を
2022年4月1日より成人年齢が18歳に引き下げられました。それによるメリットもありましたが、実情として退所後にすぐに成人した大人として、社会に出ていかなければならないことに不安感を抱えている児童が多くいます。
その不安感をなくすために、施設でもインケアやリービングケアに取り組んでいますが、残念ながらすべてを払拭できているわけではありません。残った不安感は、社会に出て、失敗を繰り返しながら学んでいくことになります。失敗をしたときに心が折れないように愚痴や悩みを聞き、共に考える存在が必要です。
近年は県外に進学や就職するケースも増えていますので、子どもが生活する地域で必要な複数の機関に子どもをつなげ、一人でも多くの支援者を作るようにしています。
子どもにとって頼れる人が増えることは大きな支えとなり、退所後に感じがちな孤立感を和らげることができると考えています。自立支援専門相談員もそういった存在の1人として支援をしています。
家庭支援
措置児童の家庭支援
家族の幸せのために、より良い多様な選択肢を考えていきます
家庭支援専門相談員は、職場ではファミリーソーシャルワーカーとも言われたり、英単語を取ってFSWと言われたりします。
子どもたちは、地域から福祉総合支援センターを経由して入所してきます。FSWはその支援センターと連絡を取り家庭復帰をすることを目標とするのか、施設からの自立退所を目標とするのか、また最近では養育家庭(里親さん)に繋げていくことを目標とするのか。FSWは、その目標に沿って家庭(保護者)とのやり取りをしていきます。
子どもにとって唯一無二の家庭との繋がりを大切にして親子の関係性や課題を理解して子どもと保護者との状況に応じた関係を支援していきたいと考えております。また、施設だけではなく親子を支える機関として福祉総合支援センター、学校、医療機関、市町村等などの支援者と協力して親子関係バックアップをしていきます。お気軽にご相談してください。どうぞよろしくお願いいたします。
地域の家庭支援
地域の子育て支援に対する相談援助
子どもの周りには様々な大人が存在します。子どもは大人たちとの相互の関係のもとに育ちます。そのため周囲の大人(保護者)の抱える背景を理解し支えるために地域にある多様な資源のひとつとして地域連携を図り『要支援家庭』『退所した児童の家庭』にとって必要だと感じられる寄り添い支援を行います。
退所した児童にとっては気軽に話しに行ける場所として存在し、核家族化の進行や地縁的なつながりの希薄化などが進行しています。そうしたなか孤立感を募らせないよう地域の家庭にとっては単に親の育児を肩代わりするのではなく親の子育てに対する不安やストレスを解消しその喜びや生きがいを取り戻して、子どものよりよい育ちを実現する方向となるような子育て支援を進めていきます。
家庭支援専門相談員は保護者が子育ての悩みなどを相談できるより所であり、子どもや保護者の意思を尊重した応援者でありたいと思っています。
里親支援
子ども「まんなか」社会をめざして
里親支援専門相談員を配置、児童相談所と連携して以下の業務を行っています。
〇里親家庭からのレスパイト
〇季節里親・週末里親
〇里親家庭訪問
〇里親家庭向けのミニサロン
〇里親会、里親支援機関との連携
〇里親登録会の補助 等
当会では施設内の子どもたちの成長や思いを取り入れて、児童相談所と連携を図りながら、子どもの里親家庭への措置変更も検討しています。
また、子どもたちや里親家庭が安心・安全に生活できるように幅広い意見を聞きながら、子ども『まんなか』社会の実現を目指して取り組んでいます。
ショートステイ
松山市の委託を受け、約1週間お預かりします
松山市の委託を受け、保護者の健康や養育環境など様々な理由により家庭での養育が一時的に困難になった2歳から高校生までの子どもを、約1週間をめどにお預かりする事業です。
一時預かり
愛媛県の委託を受け、最長2カ月間お預かりします
愛媛県の福祉総合支援センターの委託を受け、保護者の健康や養育環境など様々な理由により家庭での養育が一時的に困難になった2歳から高校生までの子どもを、最長2カ月お預かりする事業です。入所措置へと移行する場合もあります。